NHK朝ドラ「あんぱん」がついに終わった。今回はインスタにもアップした話の延長と、第四公園エピソードの2本立て。
筆者は朝ドラなんて興味もなく何十年も観たことがなかった。もっとも会社員時代は、朝8時と言えば一番慌ただしく駅に向かっている時間帯で、観ようにも観られないわけで。今はTVerなどサブスク的なサイトがあるけれど。今田美桜のファンを自認する筆者、4月からの「あんぱん」を観始めたらもう、ドップリ首まで浸かってしまったんである。今田美桜のみならず、戦争を題材にしたところや、筆者の生きていた昭和の時代と重ねつつ、多種多様な人間模様のストーリー展開に、いちドラマとしてもハマってしまったわけで。今回の朝ドラはかなり好評を博したようで、ネットでも毎日称賛の言葉が並ぶ。もっともネットニュースは、その人が興味のあるテーマを優先的に上位に表示させるシステムなので、鵜呑みにはできないけれど。それでもやはり「あんぱん」ロスは相当波紋を広げているみたいだ。近年での視聴率も良いらしい。おまけに筆者は「今田美桜」ロスなんである。ドラマの内容について語れば夜が明けちゃうので、ここでは控えるけれど、一個だけ。蘭子と八木の恋愛の行方が気になって仕方がない。(蘭子=河合優実、今田美桜の妹役。八木=妻夫木聡、モデルはサンリオ創業者社長)蘭子は最後に八木からプロポーズされたのだが、海外取材から帰ったら返事をするというのが最後のシーン。向田邦子氏のようにならなければと願うのみ。マジでそれぞれの登場人物のスピンオフ企画を出して欲しいぜと思っていたら、9/29から10/2までの23時から座談会とミニドラマ(?)をやるそうな。楽しみである。
朝ドラ明けの8:15からのNHK生放送に、最終回あとの主演の今田美桜が出演した。その可愛さの破壊力はメガトン級で、法令違反で逮捕したいくらいだ。ドングリが転がるようなコロコロした笑い声を聞くと、こちらも幸せな気分になってしまう。
さてその最終回は主人公今田美桜と北村匠海の夫婦役のほぼ二人だけが出る演出となった。乳がんに冒され余命3ヶ月と宣告された(これは史実)今田美桜は言う。
「もう今年の桜は見れないかもね」(高知弁で)
でも奇跡的に元気になってその後5年間生きたそうだ。美しい桜の下を夫婦で犬と散歩するそのシーンが下の画像。
桜に対するネットの反応はない。詮索邪推確定好きのネット民たちの指摘がないのである。何か?筆者はすぐに想起したんである。脚本の中園ミホ氏のアイデアかディレクターの演出か。「たまるか〜」だった。
「美しい桜の下を...」
なぬ?美しい桜だと?...美桜...今田美桜じゃんか!
最後のシーンを観終わった後は、清涼感と達成感と寂寞感、寂寥感の入り混じった複雑な感覚であった。いわゆるロスが半端ない。
...
さてここからは現実に戻って少年野球ブログ、「晴耕雨読」なんである。第四公園にまつわるエピソード2連発。新QueensTシャツを現在鋭意企画中なんである。今回は筆者はクリエイティブディレクターになり、デザイナーはQ母Horikoshi母なんである。普通なら筆者の仕事だが、Horikoshiさんがグラフィックデザイナーと知ってデザインをお任せすることにした。土曜仕事があったがその打合で第四を訪れたんである。着いてみるとマウンド後ろで何やら発掘作業をしていた。不思議なヒモの正体は水道栓(専門用語でカランと言う)が埋め込まれていたのだった。数人の父たちが総力を上げて発掘に成功。天空の城マチュピチュの水路の遺構を発見したような気分。
これで念願だったライト方面への放水が可能になった。泥を落としサビも削り再生し、再設置した。ただし蓋がないのでいちいち土をどかして使用しまた埋め戻しが必要だ。運用するには現実的ではない。
しかしなんでまた埋めてしまったのだろうか。それを柳さんに問うと、「昔は短いホースしかなかったから遠方放水に使えずに埋めた。今は延長ホースがあるから使える」だった。この写真を共有するため連盟役員LINEへアップ。すると吉川さんから返信があった。「昔子どもが怪我したので埋めた」のだそう。怪我はいけない。確かに雨が降れば土のレベルが下がり、同時にその分鉄枠が地面から浮いてしまうのは自明の理で、筆者もそれは懸念していたんである。スパイクが確実に引っかかってしまうはずだ。それなら仕方なしと元通りに埋め戻すことになった。しかし考えてみれば蓋さえあれば第一公園同様に安全に運用できるはずである。鉄板の蓋を頼むには宮前道路公園センターへの依頼が必要か。
さて第四公園もう一発。三塁側道路フェンス際の一本の木に筆者のリュックを引っ掛けた。ベンチ近くにリュックをかけるには最適の木があり、普段はそこに掛けるのだが、ここは先着順、早いもの勝ちで既に先客がいたため、道路フェンス際の木にかけたのだった。ドリンクを取りにその木に近づくと、明らかに獰猛そうな蜂が旋回してきた。ミツバチなら驚かないが、おそらくスズメバチに違いない。用心しながらスマホの望遠で撮ってみた。こんな時にもスマホは有用である。近づいて見たいのだが「蜂のひと刺し」はゴメンだ。するとどうだろう、まるで城塞の門番のように衛兵が二人、俺に睨みを効かしてガンを飛ばしていたのである。
観察すると時折付近を偵察飛行するではないか。一人が偵察から帰還すると、もう一人にバトンタッチしそいつがまた偵察飛行に飛ぶ。二人目が帰還すると、城主に忠誠を誓った忠実な兵隊のように、また微動だにせず槍を持ってじっと睨みを効かせるのであった。城を築いている木はこれ。素人目には築城してまだ日が浅いように思える。
まず速攻でQueens全員集めて近づかないよう周知した。その後Horikoshi父と倉庫からロープを引っぱり出し、規制線を張った。殺人現場の黄色いテープみたいに。途中近隣住民がワンコと散歩に来たので危険性を啓蒙し迂回させた。規制線だけでは物足りず、筆者閃いた。城塞の周囲をラインカーで包囲網を構築し更に「進入禁止」マークを描いたのだった。
「貴様らは完全に包囲されている。籠城しても無駄だ。武器を捨てて両手を挙げて出てこい。オフクロさんが泣いているぞ。さっさと降参しろ」と、ハンドマイクで叫んでやろうと思ったがやめた。すかさず宮前道路公園センターに駆除依頼の電話をしたが、土日休みで留守電だった。そして連盟役員LINEに情報提供。そこからFujisawa局長発、宮少連ALLで周知されたことは皆さんご存知のはず。
いつも思うのだが、凶暴なスズメバチや街を徘徊するクマ、池に棲む獰猛な外来種の魚類、etc。彼らには悪意はなく単に種を保存するための、または生存するための手段に過ぎない。それを殺傷し駆除しなければならないのはいつも心が傷むのである。彼らも我々も同じ「命」を持っている生物なのだから。地球上の食物連鎖の頂点に立つ霊長類人間としては、仕方ないことだ。更に言えば、頂点に立つ霊長類の中で更に頂点に立ちたいと躍起になると、ニンゲン間で戦争が起こるわけで。人間は愛すべき素敵な生き物だけれど、ニンゲンの使い方を間違えると、悪いほうへ暴走するしょうもない生き物でもある。
さて市学童真っ盛り。クラブJrとフレンズは敗退したが、その他は快進撃(?)を続けている。今週末はQのシスジャビと市学童初戦が連戦で待っている。10月は個人的旅行も控えて忙しい10月になりそうだ。

にほんブログ村
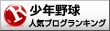
少年野球ランキング





















































